
麻雀のゲームをしていてデータの欄にある「放銃率」というワード。
今回はこのワードについて、「どんな意味なのか」という初歩的なところから、放銃率を下げるための打ち方を紹介していきます。
放銃ってどんな意味?どんな状態を放銃って呼ぶの?

麻雀のゲームでよく見る「放銃率」という言葉。
「銃を放る」と書いて放銃(ほうじゅう)と読みますが、麻雀の用語として使われる放銃は「自分の捨て牌で相手にロンアガりされた」ことを指す用語として使われます。
自分が捨てた牌で誰かがロンアガりをした際に、「○○に放銃してしまった」という言い方をするわけです。
そして「どれくらいの割合で放銃をしているか」を指すのが放銃率なのですが、その計算方法や基準などを、次の章で解説していきます。
【初心者は見て】放銃率について、計算式から基準まで
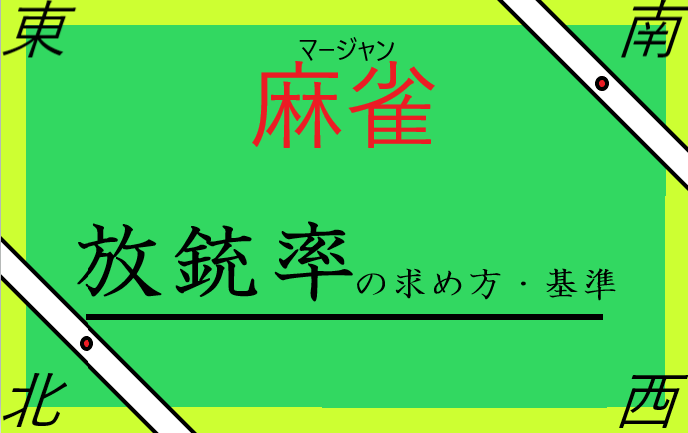
さて、自分の捨て牌で誰かがロンアガりをしたときに「放銃をした」という言い方で使う「放銃」という言葉。
「どれくらいの割合で放銃をしたのか」を表したのが放銃率ですが、この放銃率について、計算方法と基準を解説していきます。
放銃率の計算方法は?簡単?
さて、自分がどれくらいの割合で放銃をしてしまっているのかを見る放銃率ですが、その計算方法はどのようなものなのでしょうか。
その放銃率は、「(放銃した局の数)÷(全局数)×100」で算出できます。
例えば、200局行って放銃してしまったのが7局だったとすると、「28÷200×100=14」となり、放銃率は14%となります。
放銃率はどれくらいが好ましい?基準はこのくらい?
この14%という数字、放銃率で14%とすると、かなり高めの言える数字です。
ちなみに筆者は12%くらいですが、大体10%前後まで持ってこられるとOKという感じ。
麻雀ゲームなどでのデータ欄に書かれている「放銃率」はこうした計算方法から出された数字ですので、そうしたゲームで麻雀をプレイしていれば、細かく「自分がどれくらいの放銃率なのか」を探ることができるわけです。
放銃してしまうと大きな負担に。ツモアガりの3倍の支払い

本来、4人麻雀で親がツモアガりをすると、満貫をアガった場合には「4000オール」となって、子である3人が4000点ずつ払い、計12000点の親の回収となります。
この場合には1人あたりの負担は4000点。
しかしこの時に親がツモアガりではなく自分が捨てた牌でのロンアガりだとしたらどうなるでしょうか。
ズバリ、親に放銃をしてしまった自分が、12000点全てを負担しなければならないということです。
ツモアガりなら4000オールですから4000点の支払いだったところ、放銃をしてしまったために12000点の支払いとなったので、支払う点数は3倍になります。
25000点持ちからのスタートで支払う点数が3倍になるのはなかなかの痛手となるわけです。
【すぐ試せる】放銃率を下げるには何ができる?

「俺の放銃率高すぎる」とショックを受けている初心者の方も多くいらっしゃると思います。
ここでは筆者なりに、すぐに試せる放銃率を下げる方法をいくつか紹介していきます。
対策① 配牌に字牌があったら捨てずに安パイにする
自分の配牌のなかに自分には関係のない字牌があった場合、すぐに捨てるという方もいるかと思いますが、私は捨てずに何巡か回し、安全牌として持っておくことがあります。
もし東場で自分が南家だった場合、配牌に「北」があれば役牌とならないので不要な牌となりますが、1巡目で「北」を捨てるのではなく、他家が「北」を捨てたのを確認できると、それはその他家に対する安全牌となるわけです。
しかしこの作戦には欠点もあります。
それは、捨てずに字牌を持っていて、その牌がそのまま生牌となり、危険牌になってしまう場合があるということです。
もし北家がリーチをかけてきたときに「北」が生牌であれば、「北」待ちである可能性はある一定考えられるものですから、逆に危険牌になるということ。
デメリットもあるので100%安全だと言える作戦ではありませんが、放銃に加えて「一発」を回避することにもなりますから、「現物」を持っておくことは大切です。
対策② 相手の捨て牌から狙っている役を予測して牌を捨てる
もしリーチをかけた相手の捨て牌がマンズとピンズの2種類だけで、字牌もあまり捨てられていなくソウズが全く捨てられていないという状態だったら、ソウズを捨てることはできますでしょうか。
そういった捨て牌の状態になっている時点でソウズでの清一色や字牌と組み合わせた混一色が予測できるわけです。
ということは、言うまでもなくソウズは危険牌ですよね。
そのため、マンズとピンズは比較的安全度が高いと判断でき、捨て牌の優先度として高くなります。
更に序盤に捨てられた牌の周辺は安全度が高いという考え方もあるため、マンズやピンズのなかでも序盤で捨てられた牌の周辺を優先的に捨てるのがおすすめです。
上記では「清一色や混一色などの染め手」を例に挙げましたが、
・捨て牌に字牌と1・9牌が多いからタンヤオやピンフ狙いかも
・序盤から2~8の中張牌が捨てられているから七対子やチャンタ狙いかも
といった読みもできます。
対策③ 相手の現物をツモってきたときに捨てずに持っておく
中級者・上級者になってくると、相手の捨て牌を見て手が進んだことをある程度把握できることがあります。
相手が手牌から中張牌を捨ててきた場合などに「シャンテン数が進んだな(テンパイに近づいたな)」と判断が出来るので、
・手牌から中張牌が捨てられた
・ツモ切りが続いている
といった動きが他家で何度か行われれば、「テンパイしたかも」「テンパイに近いかも」と判断するようにしましょう。
このように判断できた際に、もしツモってきた牌が他家に対しての安全牌だった場合には、すぐに捨てずにその他家がリーチをかけてきたときの安全牌として手牌に持っておくことをおすすめします。
その後その他家がリーチをかけてきたときにはその牌を現物として利用できますから、「一発」の回避にも繋がります。
放銃とは?放銃率の下げ方や計算方法|まとめ|
ここまで、「自分の捨て牌で相手をロンアガりさせてしまうこと」を表す“放銃”について解説してきました。
「(放銃した局の数)÷(すべての局数)×100」で求めることが出来る放銃率は、10%前後まで落ち着かせられると「放銃率が低い」という領域となります。
また初心者の方でもすぐに試せる放銃を回避する対策もいくつか紹介してきましたので、ぜひ試してみてください。