
麻雀のルールとして知られる、「ポン」や「チー」。
対局していて相手のプレイヤーがポンやチーをしているのは見るけど、自分でやったことは無いという初心者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、麻雀をやるうえで、麻雀の戦略を立てるうえで必要な、ポンやチーについて解説していきます。
スポンサーリンク
麻雀の「ポン」「チー」「カン」=”鳴き”
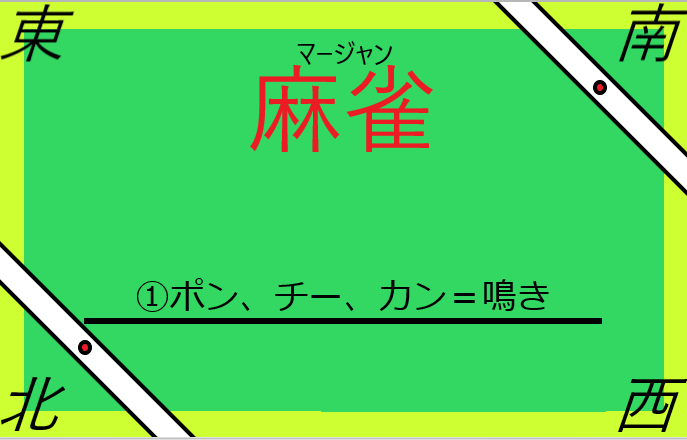
ポンやチーだけでなく、実はカンも含めて、「鳴き」という呼ばれ方をします。
麻雀の対局番組などをみていると、「ここで鳴いた」などという表現を聞いたことは無いでしょうか。
それは、ポンやチー、あるいはカンをしたという意味の実況になります。
「ポン」や「チー」など、鳴きについて解説

早速、「ポン」や「チー」について解説していきます。
鳴きというのはポン、チー、カンの3つのことを言いますが、カンについては以前ほかの記事で解説しましたので、今回は割愛。
カンについてはこちらで詳しく書いていますので、気になる方はぜひ。
www.charin07.info
スポンサーリンク
順子(しゅんつ)をつくるための鳴き、チー
麻雀というのは4つの面子(めんつ)と1つの雀頭(じゃんとう)という組み合わせて役を作るゲームです。
チートイツや国士無双(こくしむそう)など一部例外はありますが、ほとんどの場合で4つの面子を作っていくことが必要になるわけです。
そしてその面子には2つの種類があって、その1つが「順子(しゅんつ)」と呼ばれるもの。
これは、「ピンズの2・3・4」や「マンズの6・7・8」など、同じ種類の牌で数字が階段状になっている面子のことを言います。
その順子をつくるために、相手が捨てた牌に鳴きを入れて牌をとるのが、チーです。
しかし大事な注意点があり、それは「自分の左隣の相手からしかチーはできない」ということ。
この後解説するポンは誰からでも鳴くことが出来るのですが、チーはそうした制限がありますので、ご注意を。
また三麻の場合には「チーができない」というルールを採用する可能性がありますので、その場その場で確認するようにしましょう。
www.charin07.info
刻子(こうつ)をつくるための、ポン
誰かが捨てた牌を自分の牌とするための鳴きとして、ポンというものもあります。
チーというのは数字が階段状になった牌を面子とする順子をつくるための鳴きでしたが、このポンというのは3枚とも同じ牌を使って面子とする刻子(こうつ)をつくるための鳴きになります。
そしてポンの場合、左隣以外のプレイヤ―、そなわちすべての相手からポンをすることが可能。
東南西北や三元牌などは場合によって刻子とするだけで役がつきますので、低い打点でも確実にアガる確率を上げたいなどというときには積極的に活用していきましょう。
スポンサーリンク
【初心者必見】ポン、チー、カンをするときの注意点

順子をつくるチー、刻子をつくるポンですが、カンを含めたそうした鳴きには、いろいろと注意点があります。
いくつか分けて紹介していきます。
鳴きをいれるとリーチができなくなる
チーやポンなど鳴きと呼ばれる行為をすることを「鳴きを入れる」という言い方をしますが、鳴きを入れてしまった場合、テンパイをした際にリーチをかけることができません。
そのためリーチをしなくてもアガれるように他の役をつくっておく必要があるということです。
そのため役をつくることに繋がる形で鳴きを入れる必要があるということ。
例えば、
・マンズ、ソウズ、ピンズで同じ数字の順子をつくる、三色同順(さんしょくどうじゅん)
・一つの種類の牌で1~9までそろえる一気通貫(いっきつうかん)
といったことに鳴きは有効です。
しかし実は鳴きのなかでも「暗槓(あんかん)」をした場合のみ、リーチをかけることが可能。
暗槓についてはこちらで詳しく解説していますので、気になる方はぜひ。
www.charin07.info
鳴くことで翻数が下がる役がある
先ほど鳴きを活用してつくるのにおすすめな役として一気通貫を紹介しましたが、この役について、鳴きを入れない門前(めんぜん)の状態だと2翻となるのですが、鳴きを入れた場合には、1翻となってしまいます。
また混一色は門前であると3翻ですが、鳴きをいれることで2翻になります。
この他にも、清一色やチャンタなどは鳴きを入れることで翻数が下がってしまうので注意。
こうした「鳴くことで翻数が下がった状態」を”食い下がり”といいます。
食い下がりを理解していないと、「オーラスで○○点以上のアガりを決めないといけない」という状況でその条件に合うアガりを逃してしまうこともありますので、しっかりと理解しておきましょう。
スポンサーリンク
鳴いてつくった面子は崩せない
鳴いてつくった面子は自分の手牌の右側に寄せ、相手に見える状態にします。
そして一度鳴いてしまうと、その面子は崩せなくなります。
ということは、いくら鳴いてつくった面子のなかに安パイがあろうと、その牌を捨てることはできないということです。
安パイというのは防御に徹する際に欠かせないものですから、安パイになるであろう牌の場合には、そこも含めて鳴くかどうかを考える必要があるのです。
相手に狙っている役がバレる可能性
もしもソウズの牌で鳴きをいれて、河にピンズとマンズが多かったら、自然と「このプレイヤーはソウズを軸にして手牌をつくっているな」と読むことができますよね。
またそうした場合にはソウズと字牌で組み立てた混一色やソウズのみの清一色などであることが予想されますので、高い打点であると想定できます。
そのため、守りに入ると決めたプレイヤーは放銃しないためにソウズを捨てなくなると考えられるわけです。
こうなってしまうとソウズを誰かが捨てるとは考えづらくなるので、自分でツモってくるしかなくなります。
メンゼンツモがつくので1翻あがることになりますが、アガれる可能性は低くなってしまうでしょう。
まとめ 鳴きを上手く利用しよう
チーやポン、カンといった鳴きは、自分の手牌をよりよい状態にするために行うものです。
しかしリーチができなくなったり翻数が下がったり、デメリットがあるのも確かです。
また相手に自分の狙っている役がある程度バレてしまう可能性もあるので、鳴くときはそういったリスクも計算したうえで行うようにしましょう。